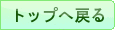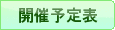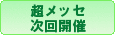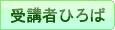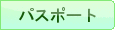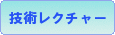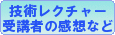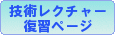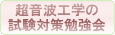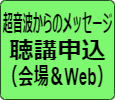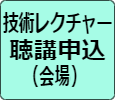��7��@�������G�R�[�Z�p���N�`���[
2023�N12��3���i���j�@�I�����s�b�N�L�O���N�����Z���^�[�ŊJ�� |
| �Ꮙ���҃R�[�X�� |
�u�t�F������ �� �i�䑷�q���m��a�@�j
��1�u�F�T�v����U
��2�u�F�`�o�@�̃|�C���g
��3�u�F����]���̌���
�A���P�[�g������@90 �� |
��7���Ö��G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
���i�v�]�j�u�`�X���C�h�̍Ō��3�����x�i�B���ʐ^�Ȃǁj�������ɂȂ�
�����̂ŁA�����炪�ꏏ�̃y�[�W���ɏC�܂��Ă���Ə����ꂵ��������
���B
�����@�ł͇@����ڐÖ��Ōċz���ϓ��i�p���X�g�`�j�A��ڐÖ��ň���
���Ɣ����@�B�G�|�Ö��ň������Ɣ���
���E���ꂼ��L�^������ł�����v6���Ƃ��Ă��܂��B�����������
�̎ʐ^���t�����܂��B
���摗���{�݂Ȃ�A�����̏ꍇ�͓�����I�X�X�����܂��B
���i�v�]�j�����Ăł���l�̏ꍇ�̎��Z�������������B
�����ł�����������Δ�I�������܂����B
���i�v�]�j���ʎ}�ƌ�ʎ}�̐��������̓s�x�����ԈႦ�Ȃ̂�����Ă���
�悭�킩��܂���ł����B
�����ʎ}�ƌ�ʎ}�Ƃ́A�Â��͕\�ݐÖ����m�A���邢�͐[���Ö����m��
���ԐÖ�����ʎ}(communicating vein)�A�\�ݐÖ��Ɛ[���Ö������ԐÖ�
����ʎ}(perforator)�Ƌ�ʂ��ėp�����Ă��܂��B
�����ʂ₤�����ɂ��Č�������K�v������̂́A�ǂ̂悤�ȏǗ�̎�
�ł��傤���H������������̌����ځA�������́H
���[���Ö�������̂ł���Η��ʂ͕s�v�ł��B�����Ö�ᎂ̊ώ@�����
���ʂ͕K�{�ł��B�������ł�����������Ό�����Ǝv���܂����A������
�̂͌����Ƃ��\��������܂��B�����̌����ڂ�����ɂ͕ς�肠��܂�
��B
�����V�^�̌����ł���Ύ����Ɖ�����������̂Ȃ̂ł��傤���B����
�Ƃ��������Ȃ��^�C�v������܂����H
�����V���ł���Ή���������̂��قƂ�ǂł��B�����ł������Ă���
���������Ƃ��Ă��܂��B
�����@�ł͊��҂���ɍ��ʂ��Ƃ��Ă�����Č�������̂ł����A���
����ʓI�ł��傤���B
�����ʂ̎p�����ۂ����Ȃ���ʂŗǂ��Ǝv���܂��B�@�������A��ڐ�
���͍��ʂ̂ق����������₢�Ǝv���܂��B
�����@�̏ꍇ�A�Q�����芳�҂��������ʂ͏o���Ȃ����߁A�㔼�g������
�N�������p���i�Z�~�t�@�[���[�ʁj�ōs���Ă��܂��B�@ �Z�~�t�@�[���[
�ʂ���t��Ō�t�Ɏ��O�m�F��ɍs���܂��B
�����ǂ��g�����Ă���ꍇ�A���nja�͌v������̂ł��傤���B��mm�ȏ�
�Ŋg���ȂNJ�l�͂���܂����B�G�|�Ö���2�{����l�ň���Ɍ�������
��ꍇ�A���|�[�g�ɂ͂ǂ̂悤�ɋL�ڂ��Ă��܂����B
���g���̊�͂���܂���B�@�����ł͂킩��₷���悤�Ɂu�g���v��
�\�����܂������A����Ö��a��葾�����Ƃł��B
���ᕶ�Ƃ��āA�w�G�|�Ö���2�{����A���̈���Ō�����F�߂�B�x����
�͒����[�̈ʒu�A�����A�P�x�A�����͈̔́A�傫����NjL���܂��B
���C���ؐÖ����ώ@���܂����H
���f���̎��ɂ����������悤�ɕG�|�Ö��̊ώ@�̍ۂɈꏏ�ɂ݂܂��B
���G�|�Ö������̂��̂͒����^�Ƃ��đS�Ĉ�t�ɑ��߂̕��K�v��
���Ă悢�̂ł����H�����̓���(����)�ɁA��ڐÖ��̌������o�����ɌÂ�
�����Ŗ��Ȃ��Ƃ�������������A�����^�Ƃ́H�Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�܂�
���B
���G�|�Ö���蒆�����i�����j�ɂ��錌���͕Ώۂł��B�������A��
���͌Â������Ȃ̂Ŕx�ǐ��̃��X�N�͒Ⴍ�ً}�Ώۂł͂���܂�
��B
����t�ɕ��K�v�Ȍ����Ƃ͂ǂꂩ��ł����Ă͂܂�Ƃ�������
�ł����H
�������^�A���V���A�����ł���A�ً}�ŕ��ׂ��Ǝv���܂��B
���@�啚�ݐÖ��O���t�g��Ƃ����I�[�_�[�ɑ��ĉ�������悢�ł�
�傤���H
���O���t�g�͐S���Ɖ����Ŏg�p����ꍇ������܂��B�ǂ�����o������
��܂���B�S����ɂ��q�ˉ������B
���A���v���[�N��Axi�ő���܂����A������Sag�ő���̂ł����H
�@��Axi�i�̎��܂��͐����f�ʁFaxial �j�@Sag�i���f�� �Fsagittal�j
�������a�̍ő�a�i���a�ƒZ�a�j�Ōv�����܂��B���a�͖��f�ʂɋ߂�
�f�ʂƂȂ�܂��B
���d������Ö��̊��҂�DVT�`�F�b�N�Œ��ӂ��邱�Ƃ͂���܂����B
�������ɂ��A�o���Ⴊ����܂���B
|
|
|
|
��43��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[
2023�N12��3���i���j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F�߉����u�i�V�Y���Ղ̖�N���j�b�N�j
��P�u�@�X���S�̂�`�o���邽�߂̋ߓ�
��Q�u�@�R�c��������Α��v�@�̊O�_���̌���
��R�u�@�����������̂��I�B���̕`�o�ƕ]��
�A���P�[�g������@100 �� |
��43���G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�����X�ǂ̑���i�摜�̏o�����j�ɋ�J���Ă��܂��B�f�v�X15cm�ŒT��
�Ă���t���[�Y���Ċg�傷�邩������x�g�債�Ă���T�����ق�����낵
���ł��傤���H
���܂��A���X�ǂ�T���i�F������j�̂͒Z���f�ʂŌ�����������ł��B��
�̎��_�Ŗڑ���3mm�ɖ����Ȃ����X�ǂ͌v������K�v�͂���܂���B��
��g�����Ă��Ȃ����X�ǂ𑪂���m���Ɏ��X�ǂ��F���ł���Z���f�ʂ�
���X�NJg���̗L�����m�F���邱�Ƃ���ł��B�����Ǝv������v�����܂�
���A���̌v���͒Z���ł������ł��v���͍\���܂���B�g�債�Čv�����Ă�
�������B�g�����Ă���ꍇ�ɂ͒������ōL���͈͂̕ω�����������ǂ���
���ˁB
���`�o���ɂ����Ɣ��f���Ď��̎�i�Ɉڂ�̂ɁA�ǂ̂��炢�̎��Ԃ�X
�L�����̉��ڈ��͂���܂����H���Â炢�����Ɏ��Ԃ����������Ď���
�̒Z�k���s���Ȃ����Ƃ������ł��B
���X����̊O�_�ǂł́A�����h�}�[�N���g���ĉf�邩�f��Ȃ��������f��
�܂��̂ŁA�P��̃g���C�ł̔��f�͐��b�ł��B��������ǂ��f��f�ʂ܂�
�̔������ɂ͎��Ԃ������邱�Ƃ�����܂��B�u�`�ŏq�ׂ܂������A���̑�
��i�X����_�ǁj��������̂ł͂Ȃ��A�u�����h�}�[�N�������đ���
�ɖڂ��ڂ��v�Ƃ��������g�ɂ��悤�ɃX�L���j���O�̍l������ς���
�Ɨǂ��Ǝv���܂��B
|
|
|
|
��5��@���G�R�[�Z�p���N�`���[ ��
2023�N9��17���i���j�@�I�����s�b�N�L�O���N�����Z���^�[�ŊJ�� |
| �Ꮙ���҃R�[�X�� |
�u�t�F���c�@�I���i���ۈ�Õ�����w���c�a�@�j
�u�t�F������@���i�䑷�q���m��a�@�j
��P�u�@�ӊO�ƒm��Ȃ����̊�b
��Q�u�@�g�`�ƃv���[�N�]���͂���������
��R�u�@�����Ēm��ׂ��b��B�̎���
�A���P�[�g������@100�� |
��5�����G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�������ɂ�IMT�͂Ȃ�ׂ����s�ɁH�ƌ����Ă��܂��������ɑ��ĕ��s��
����̂ł����H�v���[�u�����������Ă܂ŕ��s�ɂ���̂Ƃ��Ȃ��̂Ƃ�
�́A�ǂ�ȈႢ���o��̂ł����H
���̕\�ʁi�畆�j�ƂȂ�ׂ����s�ɂ����IMC�\�ʂɒ����g�r�[�����^��
����������AIMC�\�ʂ̋��E�����Ăɕ`�o���ꐳ�m��IMT�𑪒�o���܂��B
�������A�֍s�ɂ��^������������Ȃ��ꍇ�A�Ȃ�ׂ����s�ɋ߂���Ԃ�
IMT�𑪒肷��̂��]�܂����ł��B
���J���[�̃Q�C���A���������W�A���g�����ǂ��e������̂�����̐���
�����H�����܂����������ĂȂ��̂Ő������Ăق����i�����ł������Ȃ�
�Ƃ����Ȃ��Ǝv�����j��{�I�Ȃ��Ƃł����A�������J���[�Ő��Ȃ�i��
������j�̂�������Ȃ��ł��B
���@�J���[�Q�C���Ƃ́A�J���[�Q�C�����グ�邱�Ɓi��������������j
�ŃJ���[�̏�肪�悭�Ȃ�܂��B���̋t�ɒႢ�ƃJ���[��肪�����ł��B
�ō������`�o�̍ۂɂ����������ʂ�A�J���[�Q�C�����������܂��B
�@ �A���������W�Ƃ͂ǂꂭ�炢�̗�������J���[���\������邩�ł��B
���������W��Ⴍ����i��̓I�ɂ͒ō������̎��A10cm/s���x�ɂ���j��
�x�������ł��J���[�h�v�����\������܂��B
�@ �B���g���ɂ�B���[�h���g���ƃJ���[���g���Ƃ�����܂��B�J���[���g
����Ⴍ�i�@��ōł��Ⴂ���g���j�ݒ肵�Ă����ƂŐ[���܂Œ����g����
���A��r�I�J���[�\�����e�ՂɂȂ�܂��B�����ݒ�Ŏ��g����Ⴍ���邱
�Ƃ��I�X�X�����܂��B
�@ �C�J���[�\���Ƃ͌������Ă���̂�ԁA��������ق���ɕ\������
���B�����ł��������鎞�͐ŕ\������܂��B�Ö����������Ă���ΐԂ�
�\������܂��B
���ΊD���������Č����Ȃ��Ƃ��ɂ͂ǂ�������悢���킩��܂���B�R
�c������B
���v���[�u�����[�e�[�g���āi�O�ʂ�w���ɓ��Ăāj�ΊD��������
������T���Ă݂ĉ������B
�S�����ɐΊD��������ꍇ�͓��o�]���͂ł��Ȃ��̂ŁA�ΊD����艓�ʕ�
�̗����𑪒肵�ėL�Ӌ��������m�F���ĉ������B
�����������40�����炢�ł������ACCA�AICA�AVA���肷�邲�ƂɊp�x��
�����Ă��܂����H
����{��60���ȓ��Ƃ��܂��B�����̍��E���͊p�x�ɂ��e������
���B�܂葍����ō������ȂǑ���̍ۂɂ͍��E�Ƃ������p�x���]��
�����ł��B�p�x���t���ɂ������ɂ͗Ⴆ�Α����Ȃ�60�����x�A����
���A�ō������Ȃ�50�����x�ƌŒ肵�đ��肷��ƍ��E�����Ȃ�����o����
���B
����b��B������PSV��������悢���H�@�g�`�́H
�����k���ő嗬���iPSV�j�̂ݑ��肵�܂��B�g�`�͔����������Ă��邱
�Ƃ��m�F���Ă��������B����̕��ł����20�`30cm/s�ȉ��ł��������Â�
�o�Z�h�E�a�ł�50cm/s���邱�Ƃ�����܂��B
���b��B�̃`���[�gP14�̔X�E���̃`���[�g�ł����A�[���������������
���̏[��������50���͕����̏[�����𑫂��ĂƂ������Ƃł����H
���[����������������ꍇ�A�S�Ă̖ʐς𑫂��Č����ڂŔ����i50���j
�ȏ�����ꍇ�ƂȂ�܂��B
�����E�b��B���݂�ہA�����p�߂͂��܂茩�܂��H
�����̏ꍇ�A�����p�ߊώ@�͂��܂���B�b��B��{���B�̊ώ@����
��Ȃ�������p�߂̗L���̊ώ@�͕K�{�ƍl���܂��B
|
|
|
|
��42��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[�@�@
2023�N9��17���i���j�@�����I�����s�b�N�L�O���N�����Z���^�[�ŊJ�� |
| �Ꮙ�S�҃R�[�X�� |
�u�t�F�߉��@���u�i�V�Y���Ղ̖�N���j�b�N�j
��P�u�@�X�N���[�j���O���������m��
��Q�u�@�̑��̎��p�Ƃ��̍U���@
��R�u�@�]�ԑ������}�X�^�[����
�A���P�[�g������@100�� |
��41���G�R�[�Z�p���N�`���[����u����������A���P�[�g�ł���
����������Ɠ��� |
�E������u�`�Ő����ł��Ȃ��������ƂɁA��������̎�������������܂�
���B
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�������̍ۂɊ̐t�R���g���X�g�̉摜���A�̑��E�t�̊̉���`�o����r��
�ŎB���Ă��܂������A�Ȃ��Ȃ����̈ʒu����Ƃꂸ�A�]�Ԃ���Ƃ邱�Ƃ�
�����̂ł����A�`�o�����Â炭���Ԃ�������܂��B�]�Ԃ���̐t�R���g��
�X�g���Ƃ���@�������Ă��������B
���̐t�R���g���X�g�̒f�w���i�̉E�t�ƉE�t���ЂƂ̒f�ʂʼnf���j�́A
�팟�҂̑̌^�Ȃǂɂ��]���|������B��Ȃ����������ł��B�]�Ԃ���B
��ꍇ�ɂ��̒f�ʂ���肭�o�Ȃ����ɂ́A�@�v���[�u���\���ɔw���̘]��
�ɓ��ĂĂ��邩���`�F�b�N���Ă��������B���̂��߂ɂ͑̈ʕϊ��i������
�ʁj�ɂ��Ă���f�����Ƃ������ł��B�ǂ��炪�ǂ����͊��҂���̏�
���f���܂��B���ɂ͔����ʂʼnf���ꍇ������܂��B���ꂩ�������A��
�����Ă������ɉf�����Ƃ�����ꍇ�ɂ́A�]�ԑ����ł̊̉E�t�ƉE�t��
�f�w����ʁX�ɂƂ���2��ʂŕ��ׂ����ł���肠��܂���B���̎�
�ɂ͓����Q�C���ŎB�e���Ă��������B�i���̕��@�ōs���Ă���{�݂�����
�ł��j�v����Ɋ̑��ƉE�t�̋P�x����r�ł���Ηǂ��̂ł�����B
����ᎁA��ᇗl�a�ς̌v���̎d���������Ă��������B��y�ɂ���đ����
�d��������č����Ă��܂��B�i�}�����Ă̎���ł��j
���v�����ő�a�i���Ӂj�̈�����Ŏ������A�ő�a�ƍő�a�ɒ�������2
�����i�Ⴆ�Ώc�~���j�Ŏ������ƌ����₢�ł��ˁB���B�̎�ᎂ̏ꍇ�ɂ�
�u�f�w���ɂ����āA��ᎂ̍ő�a��L����ʁi�ő�a�ʁj�Ƃ���ɒ�����
��ʂŌv������B�v�i���B�����f�f�K�C�h���C���G���{���B�b��B�����g
��w��j�Ɩ��m�ɒ�߂��Ă��܂����A�����̎�ᎂł́A�v�����@�ɂ�
�Ď������K�C�h���C��������܂���BCT�Ȃǂ̉摜�f�f��a���f�f�ł̌v
���Ɠ��l�ɒ����g�ł��ʏ�́u�ő�a�v�݂̂ŕ\�����A�~�`�łȂ��i���~
�`��s���`�j�̎�ᎂ̏ꍇ�ɂ́u�ő�a�Ƃ���ɒ�������a�v�ŃT�C�Y��
�v���l���c���Ă��܂��B�����炭���Ȃ��̐�y���̌������@����ʂ肠��
�̂͂��̂悤�ȗ��R���Ǝv���܂��B��ᎂ̃T�C�Y���u�ő�a�v�Ŏ�����
�u�ő�a�~��������a�v�Ŏ������A���邢�͕��p���邩�́A�{�ݓ��œ���
���Ă���Ζ��Ȃ��Ǝv���܂��B
����y�Ɣ�ׂ�ƁA�B�����ʐ^���ڂ₯�Ă���l�Ɍ����܂��B�p�L�b�Ƃ�
���ʐ^���B��R�c����������Ă������������ł��B���Ԃ�A�ʐ^���B��
�Ƃ��Ɉ������ɂ�ł��܂��̂�������܂���B
�����Ȃ��̎B�����摜�����Ȃ��ƕ�����܂��A�������u���g���Ă���
���摜���ڂ₯��̂́A�ȉ��̗l�Ȍ������l�����܂��B�@�t�H�[�J�X��
���킹�Ă��Ȃ��B�A�摜���t���[�Y�i�~�߂�j���ɂ��Ȃ��̎�Ԃꂪ�N��
�Ă���B�B�t���[�Y�̍ۂɊ��҂���̓����i�ċz�j���~�܂��ĂȂ��B�C��
�w�E�̂悤�Ƀv���[�u�̈����̋�⑽�d���˂Ȃǂ̃A�[�`�t�@�N�g�ɋC
������Ȃ��X�L���j���O���Ƃڂ₯�Ă��܂��܂��B
���߉��������{�f��12���ŋ�����邱�Ƃ�����Ǝv���܂����A��X
���S�҂�12���������ƂȂ��Ȃ�OK���ꂸ�A�u�����ƌ����́H�v�ƌ����
�邱�Ƃ������ł��B����搶�̗l�Ȋ�{�f�ʃ��[�`���ʐ^�ȂǍ���ĉ���
��Ƃ��肪�����ł��B
�����ǂ��̎{�݂ł̓X�N���[�j���O�ł̕K�{�f�ʂ�12�����Ɍ��߂Ă��܂�
���A���S�҂��g���[�j���O����Ƃ��ɂ͋���I�ȖړI�Ŋ�{�f�ʂ͂����
�葽���B��悤�Ɏw�����Ă��܂��B�L�^�����͏��Ȃ������������Ԃ͒Z�k
�ł��܂��̂ŁA��l�O�̔��f�͂ƋZ�ʂ�����̂Ȃ�ނ�݂ɑ��₳�Ȃ���
���D�܂����ł��B�����̉摜���L�^�����Ƃ��Ă������ƌ������ɂ͂Ȃ�
�Ȃ�����ł��B�v�͎{�ݓ��Ō����Z�t�Ɣ����Řb�������Ċ�{�f�ʂ�
�ꂷ�邱�Ƃ���ł��B�����Ƃ̐M���W���K�v�ł��傤�B
���w��ɎQ�������ۂɗ�������̏�ɒu�����������������₷���ƕ����A
���H�������A�r�Ř]�ԑ������s���ɂ����Ȃ�܂����B����͓��̏�Ƌ���
��A�ǂ���̕����ǂ��̂ł��傤���H
����{�I�ɂ͎�͓��̏�̕��ɒu�������ǂ��Ǝv���܂��B���R�͂��Ȃ���
�����Ă���悤�ɘ]�ԑ��������₷������ł��B
���B����`�o����ۂɁA����̌��C��ł��B������ʍ��ɕ`�o���Ă��܂�
�����A�B�����E�ɕ`�o������@�ō��܂ł���Ă��܂����B�ǂ��炪�K��
�̂ł��傤���B
�����_���猾���Ɓu�ǂ���ł��ǂ��v�ł��B���{�����g��w��̕\���@��
���[���ł́A�c�f�ʂł͓��������ɁA���f�ʂł͉E�������ɕ\�����錈��
��ł����A�B���̕`�o�͎ߒf�ʂȂ̂ł�����c�Ɖ��߂��邩���Ɖ��߂�
�邩�œ�ʂ�̕\�����@�����݂��܂��B
|
|
|
|
��41��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[�@�@
2023�N7��23���i���j�@�����I�����s�b�N�L�O���N�����Z���^�[�ŊJ�� |
| �Ꮙ�S�҃R�[�X�� |
�u�t�F�Y�R���I�q�E�����葏�E���c�I��
��P�u�@��U�̕��@�E���K
��Q�u�@�v���[�u�������̗��K�@
��R�u�@������B���邽�߂��o���邱��
�A���P�[�g������@100�� |
��41���G�R�[�Z�p���N�`���[����u����������A���P�[�g�ł���
����������Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�� ��U�̕��@�E���K���@
���X���̕`�o�����ł��B�����ꕔ�A�����̕`�o�����Ŏ��ӑg�D�Ƃ̋�
�������܂��ɂȂ��Ă��܂��A�����X���������Ă��܂����肷�邱�Ƃ���
��A�����Ɏ�ᎂ�����ƕ|���ł��B�X�N���[�j���O�̃R�c�͂���܂����B
���X�̋��E����������Ȃ��Ȃ����ꍇ�́A�m���ɂ����܂ł͎�����������
�낤�Ƃ������܂Ńv���[�u�����Ă��������B
�܂��A���̍ۂɌǗ����̎�ᇁi���ɒ�G�R�[�̂��́j���������ӎ����Ȃ�
�猩��ƌ����Ƃ�������Ǝv���܂��B
�������p�߂���債�Ă���ہA�̑��ƋP�x�����Ă���̂łȂ��Ȃ��C�Â�
�Ȃ����Ƃ�����܂��B�X�N���[�j���O�̍ۂɒ��ӂ��邱�Ƃ͂���܂����B
�������p�߂��G�R�[�P�x�̈Ⴂ�ŒT���̂ł͂Ȃ��A�Ǘ����̍\����������
�����ӎ�����ƌ����₷���Ȃ�Ǝv�����܂��B���̍ہA�����E�Z������
�Ŋώ@����̂��d�v�ƂȂ�܂��B
�܂��A�����p�ߎ��̍D�����ʂ͌����Ă���̂ŁA�D�����ʂ�����ۂ�
�����p�ߎ�傪���鎖��z�肵�Ċώ@����ƌ��o�����オ��Ǝv���܂��B
���N�C�m�[���ނɋ�킵�Ă��܂��B���ǁE�喬���w�W�ɂ���̂͂킩���
�ł����A���ȏ��̉�U�ƃG�R�[�摜�����т��Ȃ��ł��B
���܂��͂����Ȃ�N�C�m�[���o���悤�Ƃ���̂͂�߂āA�������`�o����
���ǁA�喬�����ȏ��ɉ�U�̂ǂ��ɂ�����̂����o����悤�ɂ��Ă݂Ă�
�������i���ɘ]�Ԃ���̕`�o�j�B
�C�ӂ̌��ǁE�喬���o����悤�ɂȂ�ƃN�C�m�[�̕��ނ�������₷����
��Ǝv���܂��B
���v���[�u�̑����̗��K�@ ��
�����K�ő̂�݂��Ă��炤�Ƌ�ʂŘ]���|���Œɂ��ƌ����Ă��܂���
���B�͂̓��ꂷ���ł��傤���H�]���ɓ��Ă����ł��傤���H�@���l�⋳��
�Ă����l���������킩��Ȃ��ƁB�ɂ��Ȃ����@�������狳���Ă�����
���B
���ɂ݂̌����͍��ɓ������Ă��邩�A�����������Ă��邩�̂ǂ��炩�Ǝv
���܂��B
�v���[�u�������������ɂ��炷���A�P���ɗ͂���߂�Ɖ�������Ǝv����
���B
���c�����Ɖ��������J��Ԃ��ƃv���[�u���t�ɂȂ��Ă邱�Ƃ������ł��B
�C��t���邱�Ƃ͂���܂����H
��������c�͎��v��]�A�c���牡�͔����v��]�ɂ܂킷�A�Ƃ��������ӎ�
���Ă݂Ă��������B
���������キ�A�̑�������ۂɑ����Ă�������ƈ��荞�܂Ȃ��Ɨ͂�����
�Ȃ���������܂��B�R�c�͂���܂����B
���̏d���悹�鎖���ӎ����Ă݂Ă��������B�v���[�u�Ǝ����̑̂Ƃ̋���
���߂Â�����A�֎q�̈ʒu��������������Ƒ̏d���悹�₷���Ȃ�܂��B
���u�t���͕K��2�����ŃX�L��������v�Ƃ́A�����E�Z�������łȂ��A�X
�L������������i���Ă�ʒu�j���ς���Ƃ������Ƃō����Ă��܂����B
����ʂ�ŁA���d���˂Ȃǂ̉e�����Ă���\��������̂ŁA�X�L
������������������������悢�ł��B
�������̉��̊̉��݉��̎��̉摜�́A�ǂ���ǂ����āA�ǂ�����A�v���[
�`������ǂ��������Ē��������ł��B
���S�|���c�����ŁA�̑��̃G�b�W�i�[�j������Ă��邩�ǂ������Ă�����
���B
�@�@
�� �����t���[�E�A�v���[�`�E�̈� ��
��������ʂł̘]�ԑ����ŁA��ʂŕ`�o����Ƃ����̑������ꂢ�ɏo
���܂���B�R�c�������Ă��������B
���]�Ԃ̑��s�̈ʒu�A�w�b�h�̈ʒu���m�F���Ă݂Ă��������B
���̑��̃Q�C���A�t�H�[�J�X������ہA���b�̓��̂т܂Ɋ̑���
�P�x���ω�����a�C���������Ȃ��悤�ɂ���ɂ́A���܂�Q�C���𑀍삵
�Ȃ����������̂ł��傤���B�ꖇ��ƂȂ�悤�Ȏʐ^���c�����̍H�v��
�K�v�ł��傤���B
���Q�C���̂悤�ɑS�̂̋P�x��ς�����̂ł������肠��܂��A
STC�ȂǕ����I�ɕς�����̂ł��Ǝ��b�̂̏������������\���������
���B
���_�X�̃A�[�`�t�@�N�g�͂Ƃ�Ȃ��Ƃ��̓Q�C���������Ă����v�ł���
�����H
���Q�C���������ăA�[�`�t�@�N�g�������ƒ�G�R�[�̎�ᎂ��ꏏ�ɏ�����
���܂��\��������̂ŁA�Q�C����������Ƃ��Ă�������l�����ĉ�����
���������B
���A�[�`�t�@�N�g�u�T�C�h���[�u�v�̔������Ȃǂ�������Ă���������
���ł��B�������l�E�������l�o�[�W����������Ǝ��ۂ̌����Ɋ������₷
���Ǝv���܂����B
�����͂̏����ǂ��T�C�h���[�u�̌����ƂȂ鎖�������̂ŁA�̈ʕϊ����s
������A�v���[�u�Ă�ꏊ��ς��Ă݂Ă��������B
���ޏk�t�̕`�o�@�ł܂����Ă��܂��B�B����̃R�c�͂���܂����H
���ޏk�t�́A�������ɔ������Ă���ꍇ������A�����ƃT�C�Y�〈����
���ω����Ă��鎖�������̂ŁA�܂��͂�����C���[�W����Ɨǂ��Ǝv����
���B
�܂��ǂ��̑���Ƃ��q�����Ă��Ȃ��Ǘ����̂��̂�T���悤�ɂ���Ɨǂ�
�Ǝv���܂��B
���_�X�B�؎�ǂƑB�؏ǂ��Ⴄ���̂��ƕ������̂ł����A���ׂ�قǕ���
��Ȃ��Ȃ�܂����B�Ⴂ�������Ă����������炤�ꂵ���ł��B�i���ׂ���
�����킩�邩��A�A�A�ƌ����܂����j
���_�X�̕a�ς́u�_�X�B�؎�ǁv���������ł��B�u�_�X�B�؏ǁv�Ƃ�����
�͌�p�ƍl�����܂��B�B�؎�ǁi�_�X�Ɍ�����ω��j�ƑB�؏ǁi���
�q�{�Ɍ�����ω��j�́A�a���ł͕ʂ̕ω��ł��B���t�����Ă���̂Ō�
�p�����Ă���̂ł��傤�B������l�b�g�̋L�ڂł��������Ďg���Ă����
�̂������Ό������܂��̂ŁA�f�킳��Ȃ��悤�ɂ��Ă��������B
���������Ԃɂ��ăV�r�A�Ɏw������Ă���܂��B�����Ō��ꂽ��ł�
�邾���̈ʕϊ����Ȃ��悤�w������Z�t������̂ł����A���������Ă���
�������̈ʂ͖���K���s���ق����ǂ��ł��傤���H(�l�ԃh�b�N�ł�)
�����������Ō���ƁA���ɂ������킪����̂Ō����̐��x�����������
�Ȃ�̂ő̈ʕϊ��͖���s���������ǂ��ł��B
�̈ʕϊ��ɂ��Ă͂��܂��܂ȍl����������܂����A�����Ƃ������Ȃ���
�Ȃ�A���ꂼ��̑̈ʂłǂ̑��킪�����₷�����c��������ő̈ʕϊ���
�s�����ƂŒZ�����ԂŌ����ł��܂��B
|
|
|
|
��10��@�S�G�R�[�Z�p���N�`���[
2023�N3��22���i�j�j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F��ԁ@�[�i������@�@�z����ȁj
��P�u:�����R��̂Ȃ�������f�����s��
��Q�u:�T���������A�v���[�`
��R�u:�S�땔�E�S�|���A�v���[�`
�A���P�[�g������@95��
|
��10��S�G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
��SV�̑���l�@RVOT�ALVOT�A�QD�A�f�B�X�N�@�ŕs��v���������Ƃ��A��
�̕��@���ǂ��������̗p�ł���̂��H
���@�厖�Ȃ�����ł��B�ǂ̑���l��M���ł���̂��ɂ��ẮA������
�p�������@�ł���A�ϓ��Ȍ������L�^�ł��Ă���ꍇ�͍̗p���܂����A
����f�ʂŗ����ɕ肪����ꍇ�͗p���܂���B�f�w���狁�߂鎞�́A�K
�Ȓf�w�ʂ��Ƃ炦���Ă��Ȃ���̗p���Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B�e�X
�̌v���l��M���ł��邩�ǂ����ɂ��ẮA���N�`���[���ɂ��b�����܂�
���̂ōĊm�F����������Ǝv���܂��B
��sigmoid�̎�RVOT���`�o�s�ǂ̏ꍇ�A2D�ƃf�B�X�N�@�ŕs��v�̎��Ȃ�
���@�Q�c�ƃf�B�X�N�@�ŕs��v�ɂȂ�̂́A�lj^���ُ킪���鎞��������
�v���܂��B�q�u�n�s�̕`�o�ɂ��ẮA�T���������ŕ`�o���ɂ������ɂ�
�S�|������A�v���[�`����Ƃ��܂��������Ƃ������ł����A����̃��f��
�N�ł͂������ł��Ȃ��Ăb�n�o�c�̐l�ł͕`�o�ł��邱�Ƃ������ł��B
���E���@�\�̕]����TAPSE��RV focus view�As'�͏C���E���H��view�Ōv
������i�����j���R���m�肽���ł��B�K�C�h���C���I�ɁH
���@�K�C�h���C���ł�������Ă��܂����A�E���S�̂��`�o�����f�ʂŌv
�����邱�Ƃ���������Ă��܂��B�܂��A�E�����R�ǂƎO��ق̃q���W�̕�
���̓������ł����f�ł��邩�炾�ƍl���Ă��܂��B
���Z���ō����v��������Ƃ��̈ʒu�������Ăق����B�搶�̖{���ēx��
�Ă݂܂��B
���@�����f�ʂƓ��l�ɑm�X�ق̐�[�ɂȂ�Ɨ������Ă��܂��B
����������������4�`�����o�[�A�R�`�����o�[���ꂼ��v�����Ă��܂���
�l���قȂ��Ă��܂����Ƃ��͂ǂ�����̗p����悢�ł��傤���H
���@�������������𐳖ʂ���Ƃ炦�邱�Ɓi����������^�������Ƃ炦��
���j���ł��������̗p����Ƃ����Ǝv���܂��B
������҂�4�`�����o�[��`�o���悤�Ƃ����5�`�����o�[�����`�o����
�܂���B���̎���RA�ALA�̌v���͂ǂ̂悤�ɍs���悢�ł��傤���H����
���4�`�����o�[�ɂ���Ə������Ȃ��Ă��܂��܂��B
���@�悭�킩��܂��B�S�|������A�v���[�`����ƓK���Ȓf�ʂ������邱��
�����L��܂����A�v���ł��Ȃ����Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ǝv���܂��B
|
|
|
|
��40��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[
2023�N3��22���i�j�j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F�߉����u�i�V�Y���Ղ̖�N���j�b�N�j
��1�u�@�߂Â��čL������������
��2�u�@�{���͂��킢�t���̕`�o
��3�u�@����Ε��������t�̕`�o
�A���P�[�g������@95�� |
��40���G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�� �����ǂɈ����̏������������ꍇ�̊ώ@�̍s�����B�T�C�Y��ǂ̌����A
�J���[�̓��ĕ��Ȃǂ킩��Ƃ��肪�����ł��B
���a�ς��������Ƃ��̊ώ@�i�����j�ɂ��Ă͂��܂肨�b���ł��܂���
�ł����B����͗��ӂ������܂��B
�a�ς��������Ƃ��ɂ́A�@�\���Ɋg�債���摜�Łi�ł�������g�v��
�[�u���g���āj���������ƒZ�������̉摜���c�����ƁB�A���ǂ̏ꍇ�͂�
�܂�T�C�Y������̌v���ɐ^���ɂȂ�K�v�͂���܂���i�Տ����Ƃ���
���̕K�v���������Ƃ������ł��j�B�B�J���[�h�v���ł̊ώ@���s������
���W���邱�ƁB�����ĕa�ς̎��͂̕t�я����ώ@���āA����������Ή�
���Ɏc�����Ƃ���ł��B
�� �̐t�R���g���X�g�ŁA�̂Ɛt���ꏏ�ɕ`�o�ł��Ȃ��Ƃ��́A�����ڂ̊�
���̃C���[�W�ŕ]�����Ă悢�̂ł��傤���B
���̂Ɛt�����ʂŕ`�o�ł��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�Q��ʂŎB���ĕ��ׂĂ��\��
�܂���B�Q�C���͕ς����ɓ��������ŎB�����̂Ɛt���ׂĂ��������B
�� �G�R�[�����ӂłȂ��h�N�^�[�ɏ����Ƃ��ĕ���Ɓu�����ł����H�v
�ƕ������̂ŁA�t���̋U��ᇂ͏����Ƃ��Ď��Ȃ��āi���Ȃ��āj
���ǂ��̂ł��傤���H
�����Ȃ��ƌ����������Ȃ����F�����Ȃ��������ƂɂȂ肩�˂܂����
�ŁA�͂��ׂ��ł��B�Ⴆ�u���t��ᎏ�̕ό`�i����j����v�ƋL��
���c���Ă͂������ł��傤�B
�� �E�̕��t�̈�Ɏ�ᎂ����邪�A�̗R�������t�R�����Y�ނ��Ƃ������
���B�ċz�Ŋ̂ƘA�����ē���������Ƃ����ƕ��������Ƃ����邪��������
���傤���H
��3�p�ȉ��̎�ᎂ��ƌċz�ړ��ɂ��Y���̗L���ŗR������������̂͂�
�Ƃ̕��@�ł��B�ł����₵�����̌�����ᎂ́A����ȏ�̑傫�Ȏ�ᎂ�
�ꍇ�ł��傤���B�傫�Ȏ�ᎂł̓Y���������Ȃ����Ƃ������ł��B���̏�
���ɂ́A�̑��Ƀr�[�N�T�C�������邩�A��ᎂ̌������̓��̌��ǂ��痬��
����Ă��邩�Ȃǂ��R������f������ɂȂ�܂��B
�� �e�L�X�g�ɔA�ǂ��ڂ��Ă����̂ŕ������������B�tg�����Ă������
�A�ǂ��r���܂ł����ǂ��Ȃ����Ƃ������̂ŁA�@��������畷�������B
���A�ǂ̕`�o���ȑO�̓J���L�������ɓ���Ă����̂ł����A����́i�g��
�̂Ȃ��j�A�ǂ̕`�o�͓�Փx����⍂����ɁA�g���̂Ȃ��A�ǂ����邱��
�͂قƂ�LjӖ����Ȃ��̂Ō��݂͎����ŋ����Ă���܂���B�A�ǂ̕`�o��
���t�̕`�o�Ǝ��Ă��āA��U�ƃ����h�}�[�N�𗝉��ł���i�g�������j
�A�ǂ̕`�o�͓������܂���B�������Q�l�Ƀg���C���Ă��������B����
�̔A�ǂł����Ă���U�ƃ����h�}�[�N�𗝉�����Ηv���̕`�o�͉\��
���B
|
|
|
|
��6��@�������G�R�[�Z�p���N�`���[
2022�N12��18���i���j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F������@���i�䑷�q���m��a�@�j
��1�u�@��������Ό����������@�̃R�c
��2�u�@������������������]��
�A���P�[�g������@100 �� |
��6���Ö��G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�y���ځE�q�����ؐÖ��̈�z
���q�����Ö��ɓ����A�����A�O���̌��������������Â炢�����Ƃ悭��
����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�܂�������������������Ɗ������ł��B
���i�����}�j�C���Ö��ɍ������邱�Ƃ������A�������C���̊ԁi�ӂ����
���̒����j�𑖍s���܂��B
�i�O���}�j�C���Ö��ɍ������邱�Ƃ������A�C���̊O���𑖍s���܂��B
���q�����ؐÖ��͂͂����蕪����Ȃ��ꍇ�A�g�����Ă���ӏ����Ȃ���
���猌���͂Ȃ��Ɣ��f���ėǂ��̂ł��傤���H(�Ԃ��Ă݂�K�v�͂Ȃ�
��)
���g�������Ö��͌����Ȃ��ꍇ�A�����Ȃ����A�������Ƃ��Ă��ɂ߂ď���
���Ǝv���܂��B
�����ڂ����������ɂ����ƌ���ƌ����Ă��܂������A��P�x�����͈���
���Ȃ��Ƃ킩��܂��A�ǂ����Ă���̂ł��傤���B
����P�x�����͈����@�Ŋm�F���܂��B�����Ƃ݂Č��NJg��������Ό�����
�^�킵�������@�Ŋm�F���Ă��܂��B
���O���������Ȃ��Ă͍s���Ȃ����͂ǂ�Ȏ����H
���q�����ؐÖ�������������Ö��A�C���Ö��Ɍ���������ΑO�����Ö���
�݂��ق����ǂ��ł��B
�y��ڕ��E�����̈�z
����ڐÖ��ɔ����Ǎ������ώ@����鎞������܂����A����͌�����
��������Ɋ펿�������A���̂ƍl���Ă悢�̂ł��傤���H
���펿�����������Ǝv���܂��B
���u�`�̒��ŕǔ���ƕǍ����̈Ⴂ�͗����ł��܂����B"
�����������̏ꍇ�A���Ǖǂ��s�ψ�Ȃ�܂��B����̏ꍇ�͋ψ�ł��B
�������Ǎ����ł͈ꕔ�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���H
�������Ǎ����͈ꕔ�܂��͑S�̂��������Ǝv���܂��B
�����������p��ŋ����B��ɂ�葍�������Ö������ɂ����Ƃ��������
�����B����mass�Ȃǂő��������Ö����Ȃ��Ƃ��ɂ͂ǂ������猩�₷����
��܂����H
���얞�̌^��D�w����̏ꍇ�A����������A�v���[�`���܂��B�E��������
�ꍇ�A������ʂɂ��đ������̉��݂���A�v���[�`���܂��B����ł��`�o
����̏ꍇ�A�����g�����ł͕`�o����Ƃ�CT���̌������]�܂����Ǝv���
�܂��B
�y�����@�z
���w�b�h�A�b�v���Ă��Ђ�ߐÖ��������Ȃ��l�͂ǂ��܂Ŋ撣���ĒT��
�悢�������ĉ������B
���Ö��͌����Ȃ��ꍇ�͋��炭�������Ȃ��ƍl���܂��B�������Ƃ��Ă���
�߂ď������Ǝv���܂��B���炩�Ɍ������Ȃ��ꍇ�A�u���炩�Ȍ����͌�
�o�ł��Ȃ��v�ƕ��Ă��������B
�����ڂ����������ɂ����ƌ���ƌ����Ă��܂������A��P�x�����͈���
���Ȃ��Ƃ킩��܂��A�ǂ����Ă���̂ł��傤���B
����P�x�����͈����@�Ŋm�F���܂��B�����Ƃ݂Č��NJg��������Ό�����
�^�킵�������@�Ŋm�F���Ă��܂��B
�����C��ł͍��ʂł͎��{����܂���ł������A���@�ʼn��ڂ͕K��(����
��l��)���ʂ��s���܂�(��ʂŌ����Ă��Ă�)�B���Ȃ��ėǂ��ł��傤
���B
���������ł�����ʂŌ����\�ł��B���@�̏ꍇ�A�Q������̕�����
�����ʂ͍���͂����ʁi�w�b�h�A�b�v�j�Ŏ��{���Ă��܂��B
����{�Z���Ō��āA���������肻���������璷���Ō���Ƃ������Ƃŗ�
���̂ł��傤���B
�������@�͒Z���Ŋm�F���܂��B�����Ŋm�F���ċL�^���Ă��܂��B
�y���̑��z
���v���̎d��
���q�����ؐÖ��̏ꍇ�A�����T�C�Y�͒����ƌ��݂𑪒肵�܂��B��ڕ�
�i�G�|�Ö��j����q�����ؐÖ��܂ł���ꍇ�A�����͑��肹�������[�Ƒ�
�ݕ��ʂ��L�ڂ��܂��B
�������̌����̏Ǘ�A���o�Ǐ�͂ǂ��ł������H
�����ڂ������ł��܂������ɂ݂�����܂���B�Ԍ�����s������܂�
��B
��DVT�̑傫���ɂ�鎩�o�Ǐ�͂ǂ��ł��傤���H
��DVT���傫���Œɂ݂��ς�邱�Ƃ͂Ȃ��ł��B�傫���Ă����Ǐ�̕���
���܂��B
�����ڕ��ɂ����������Ԃ������Ă��炤�̂͑S�̂��炷��Ɨ����Ɍq��
�邩�Ǝv���܂����B�r���[�̌������͂��ǂ����Ȃ������B
���l�I�w�����������܂��B������]��������A�����������B����͉�
��ł����₭�������B
���ċz�@�Ƃ������̂�m��܂���ł����B���̂��߂ɂ���̂��A������
���Ȃ�Ɖ��Ȃ̂��A�����Ă��������B�g�����Ă��Ȃ����ǂ����Ƃ�������
�ł����ˁH�ϓ������遁�g�����Ȃ��H
���������ł̕ǂ�����ƌċz�ϓ��̏���(����)�������邽�߁A��ڐÖ�
�ōs�������̈摤�̌����̗L�����m�F���Ă��܂��B�ڍׂ͒����g�ɂ��[
���Ö������ǁE�����Ö�ᎂ̕W���I�]���@�u�����U���@�v�̗������Q�Ƃ�
�������B
���F�̃C���[�W�͍��P�x�ɂ����ۂ���������ł����A����킵����
���͉��Ǔ��̉\��������̂ł��傤���H
���m���ɍ����g�v���[�u��������F�̈�{��{������ō��P�x�Ɍ�����
���B���ǂȂǂ̎����͏ڂ����͂Ȃ��̂ő��������܂���B
|
|
|
|
��39��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[
2022�N12��18���i���j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F�߉����u�i�V�Y���Ղ̖�N���j�b�N�j
��1�u�@�ӊO�Ɍ����Ƃ��_�X�̒[
��2�u�@����ł��m�肽���̋��
��3�u�@���łɌ��悤�����p��
�A���P�[�g������@97�� |
��39���G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
���喬�{�����ɕ`�o�����ꍇ��������̂ŁA���P�x�̎�ᎏ�̂��̂͏�
���ƂȂ�a�ςł��傤���H�����̉����̉f�荞�݂����Ă�����̂ł��傤
���H
�����̉摜�������Ă��������Ȃ��Ƃ���������̂�����ł��B�f�荞��
���܂߂Ă������̉\��������܂��B�@�����Ή摜�������Ă�����
���B
���_�X�̓��o�Œ��ɕ����Ă���̂͒_�X�|���[�v���Ă��Ƃ�����܂����H
�����Ȃ�������ǁA�lje��̔��f�Ń|���[�v�ł����B
��������摜�������Ă��������Ȃ��Ƃ�����������ł��B�u�����Ȃ���
���v�Ƃ���܂����A�ǂ�ȏ����ɖ��������������Ă��������ƎQ�l�ɂȂ�
�܂����B
���N�C�m�[�ŋ��E�ʏ�ł݂�ꂽ��ᇂ��N�C�m�\�ŕ\���ꍇ�A�uS4,5�v��
�ǂɂȂ�̂��B
�����̒ʂ�ł��B����S4-5�̂悤�ɕ\�����Ă��܂��B
������ope��̃t�H���[�ł悭����������̂ł����A�̖啔LN���(�G
���A�ג������Z�a��2~3mm)�Ə����Ă悢���̂��������Ƃ�����܂��B�{��
�͂ǂ��\������悢�̂ł��傤���B
���]�ڐ����̃����p�߂́A�Z�a��10mm�ȏ�Ɩڈ��ɂ��܂��B�̉��Ȃǂ�
�����锽�������́A�Z�a��6mm���x����L�ӂƂ��邱�Ƃ������ł��B
���ݎ��͂̃����p�ߎ����ŋߋƖ��Ō�����(�݊��̐l)�̂ł����A�X��
�������Ă���悤�Ɍ����A���^�Ƃ̊ӕʂ�US�㍢��Ƃ��܂����B�����
�����p���I�Ǝ��M���Ȃ����́uLN�^���v�Ƃ��Ă悢�̂ł����H
����������ŗǂ��Ǝv���܂��B
|
|
|
|
��38��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[�@
2022�N10��16���i���j�@��������a��قŊJ�� |
| �Ꮙ���E�����҃R�[�X�� |
�u�t�F�߉����u�i�V�Y���Ղ̖�N���j�b�N�j
��P�u�@�X���S�̂�`�o���邽�߂̋ߓ�
��Q�u�@�R�c��������Α��v�@�̊O�_���̌���
��R�u�@�����������̂��I�B���̕`�o�ƕ]��
�A���P�[�g������@84�� |
��38���G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
���X�����ɔX�E���F�߂���Ǝv�����������Ƃ���A���ǂ̈ꕔ��
�����B�����̗L���Ȃǂ͍s���Ă��܂����A�����ӕʃ|�C���g�͂���܂�
���B
���X�����̋ߖT��������܂��̂ŁA���ǂ��c���ł���ƔX�E�Ɍ�
������A��ᎂɌ������肷�邱�Ƃ�����܂��B��������ɂ̓h�v���ł͂�
���A���炭����~�߂Ċώ@���Ă���ƁA�����ł���Ό`����e���̓���
�Ŋӕʂ��邱�Ƃ��ł��܂��B
�������J�b�g�����������Ď��Ԃ��������Ă��܂��B50�J�b�g�قǂQ��
�ʂŎB���Ă��܂��B���������ǂ̂悤�ɂ��ċL�^����̂��킩��Ȃ��B��
�������Ȃ������悢�̂���y�͋����Ă���܂���B
���L�^�摜�������B�邩�́A���ǂ���搶��{�݂ł��߂邱�Ƃł����A��
���悭�i�Z���ԂŁj�������邽�߂ɂ́A�����͏��Ȃ����������ǂ��ł��B
�{�ݓ��Łu���̉摜�͉��̂��߂ɋL�^���c���̂��v�����߂čl���Ă݂邱
�Ƃ������߂��܂��B50�J�b�g�͊m���ɕ��ς�葽���Ǝv���܂��B���Ȃ݂�
���̎{�݂ł́A�����������ꍇ�ɂ�10�J�b�g���x�̊�{�I�ȋL�^�f�ʂ���
�߂ĉ^�p���Ă��܂��B
���t���t�H�[�J�X�̋@�B���g���Ă��܂����A����̃����b�g�E�f�����b
�g�������ĉ������B
���X�N���[�j���O�ł́A�t���t�H�[�J�X�Ō�������ƃt�H�[�J�X����
���Ԃ�����̂Ō����悭�����ł��܂��B�܂��[�������̉𑜓x�����肷
��̂Ŏ��F�����悭�Ȃ�܂��B�f�����b�g�͂��܂�Ȃ��Ǝv���܂��B
�����f���X�ꕔ��K�{�ɂ��Ă��Ȃ��{�݂����邪���e�I�ɂ���ŗǂ���
�ł��傤���H(�d�v����)
�����f���X�b���܂Ō��Ă��Ȃ��Ƃ����͖̂�肠��ł��B�����炭���̎{
�݂͌��f�ɂ����镠���G�R�[�̖����𗝉����Ă��Ȃ��̂ł��傤�B
�����̋Ȃ����Ă��邨�N���̕��̌��������鎞�ɑ���ʂɂ���Ɣw��
���ۂ��Ȃ茟�����s���ɂ����ł��B����͂Ȃɂ����₷�����@�������
�ł��傤���H����Ƃ��o���ł��傤���H
���x�b�h���M���b�`�A�b�v�ł���Ȃ犈�p���Ă��������B����Ȍ������
�ꍇ�ɂ͗\���̖���N�b�V������p�ӂ��Ă����A�����Ȃ��������ɂ͏��
���������Ă�����Ɨǂ��ł��傤�B���̂悤�ȃN�b�V�����́A����ɂ߂�
������ɂ͕G�̉��ɂ���č����グ��Ɗ��҂��y�ɂȂ�܂��̂ŁA��
�����̕K�v�A�C�e���ł��B
���ȑO�l�b�g�Ń~���N�e�B�[������ł��猟������Ƃ悢�Ƙb��ɂȂ�
�܂������A�~���N�e�B�[�ł���K�v�͂���̂ł��傤���H
�����̓c���K�q�搶���������Ă�����@�ł��B�i�~���N�e�B�[�@�ƌ���
�悤�ł��j�~���N�e�B�[�̕������݂₷���ׂ����C�A������ɂ����E�E�E
�Ƃ���Ă��܂����A�����@�́A�����Ŏ������悤�ɒE�C�����g���āA����
�ł��獶����ʂŋC�A�������������Ԃ𐔕������Č�������A�~���N�e
�B�[�łȂ��Ă��\���Ɍ����\�ł��B�ł�����u�K�v�v�͂���܂���B��
���E�C���́A�������łȂ���Ύs�̂̃y�b�g�{�g���̐��₨���ő��v��
���B�e�L�X�g���Q�l�ɂ��Ă��������B
|
|
|
|
��4��@���G�R�[�Z�p���N�`���[
2022�N10��16���i���j�@��������a��قŊJ�� |
| �Ꮙ���҃R�[�X�� |
�u�t�F���c�@�I���i���ۈ�Õ�����w���c�a�@�j
�u�t�F������@���i�䑷�q���m��a�@�j
��P�u�@�ӊO�ƒm��Ȃ����̊�b
��Q�u�@�g�`�ƃv���[�N�]���͂���������
��R�u�@�����Ēm��ׂ��b��B�̎���
�A���P�[�g������@100�� |
��4�����G�R�[�Z�p���N�`���[����u���������炢��������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
�����͂���ƂȂ�Ƃ��B�e�ł���悤�ɂȂ�܂������A�܂����������܂�����Ȃ��Č�����
�Ԃ̒Z�k���@���m�肽���ł��B
�������Ȃǂ̑������ǂŗ��K���Ă͂������ł��傤���B�p�x��60�x�ŌŒ肵�ăT���v��
�������ɂ���B �����ł������Ɣg�`���Ԃ�Ă��܂��̂Ŏ�̍b�����҂̔畆�⍽���Ɍ�
�����ł��B
�����̎B�e�̎��͔w���ɖ������Ȃ����������̂ł��傤���B
����{�A���͂Ȃ��ق��������ł��B�@�������̓^�I����܂��ĒႢ���ł��悢���Ǝv���܂��B
�����ǂ����₪���������悤�Ɍ��ɂ���������������Ⴂ�܂��B���̂悤�ȕ��ւ̑Ώ��@�Ȃǂ�
��܂����狳���Ă��������B
�����d���˂̉\��������܂��B�@���d���˂����������@�ɂ͉��L������܂��B
�@����Ö������̉�ʏ�̏�ɕ\��������ƌy�����܂��B
�A�[���[���߂ɂ��āA�������ɂ߂�ƌy�����܂��B
�B���u�ɂ���Ă͐ݒ�Ōy�����܂��B�e���[�J�[�ɂ��₢���킹���������B
�C���Ă�ꏊ��ς���A���Ăĕ��ʂ��O�ʂ������͌���ɓ��ĂĂ݂Ă��������B
����ECA�g�`�Őꍞ�݂�����͉����e�����Ă���̂��H���}���ǂ̉e���Ȃ̂�
���傤���H
�����k�������Ɍ����P�����g�`�ł���D�������ǒ�R�����x�ɏ㏸�����Ƃ��Ɍ����
�����ł��B
�������ɂ��ꍞ�݁i�m�b�`�Fnotch�j������̂͊O���Ɠ��z�����̗���������
�������g�`�ɂȂ��Ă��邩��ł��B
�b��B�F�B��l�b��B��Ɨǐ��B��l���߂̈Ⴂ�͑������Ă��邩�ł��傤���B
���ǐ��B��l���߂͌��߂��P���ȏꍇ�B�@�B��l�b��B��͌��߂������̏ꍇ�ɂȂ�
�܂��B
��EDratio�̏o�����������ė~�����B�����͂ǂ�����o���̂��H
��CCA�AICA�AVA�œ������ǂ̈ʒu�A������p�x�ŕ`�o���܂��B
���E�̊g�������������x�iEDV�j�̔�����߁AED ratio �� 1.4 �ȏ�̏ꍇ�� EDV �̒�
�����̉��ʑ��ɍ��x����������͕Ǖa�ρiFig.56�j�̑��݂��^���܂��B
�EED ratio�F ����EDV(EDV������) �� ����EDV(EDV�x����)
https://www.jsum.or.jp/committee/diagnostic/pdf/jsum0515_guideline.pdf
�@�@�����g�ɂ�����a�ς̕W���I�]���@2017
��ED ratio�FED ratio�̕]�����@�ACCA��1.4�ŕǂ��^���Ƃ̂��Ƃł����AICA��VA��ED
ratio�͂ǂ�ȈӖ�������܂����H
��CCA�Ɠ��l�ȈӖ�������܂��B�@�X�N���[�j���O�ő��肷��̂��L�p�ł��B���L�̂悤�Ș_
��������܂��B
�@�@�@�@�������E�g�������������x��iED ratio�j��ʉ��
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamt/65/5/65_15-102/_pdf/-char/ja
��ECA�ɋ�����ꍇ�A�ǂ̂悤�ɋ���̒��x��]������܂����H
�������g�ɂ�����a�ς̕W���I�]���@2017�ł͊O���Ɋւ��Ă͕]���@������
�܂���B
�����ł͖ڈ��œ��z�����Ɠ���PSV200cm/s�ȏ�ŗL�Ӌ���Ƃ��Ă悢�Ǝv���Ă��܂��B
���X�����g���|���߂���Ɗ��x��������̂͂Ȃ��ł����H
���X�����g�@�\�́C�X�Ίp�x���傫���Ȃ�ɘA��Č��ǂ܂ł̋����������C�h�v���r�[���̑�
��M�ʐς������Ȃ�h�v�����x���ቺ����ƌ����Ă��܂��B
���v���[�N�̑���̎d���A���̑�������Ċm�F�����������ł��B
�������g�ɂ�����a�ς̕W���I�]���@2017�@�Q�l�ɂ��Ă��������B
�����z�E�O�a�����̕��œ��z�������悶��Ă���l�������ł��B���f������������
���ǂ����Ă���l���݂����ł��B�悶��݂����ł��B
�������Ŋώ@���悤�Ƃ���ƒǐՂ�����Ȃ̂ŁA�܂����Z���ő��s���m�F���ώ@���Ă�����
���B����A�v���[�`�ŕ`�o���₷���Ȃ�ꍇ������܂��B�܂��A���z�������꒼���ŕ`�o����
���Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�˂���E���ȕ����Ƃ���ȊO�Ƃŕ`�o���Ă͂������ł��傤���B
���ΊD���v���[�N�̌����̕]�����������M���Ȃ��̂łǂ̂悤�ɂ��Ă��邩�m�肽���B
�����Ă�ꏊ��ς��Ă��s���Ă�J���[�h�v�������Ȃ��ꍇ�A�����A�e�ŕ`�o�ł��ĂȂ�
�\��������܂��B���̏ꍇ�A�v���[�N���͎Q�l�l�Ƃ������ŋ���]�����ĉ������B
���Z���ŕ\����CCA��ǂ��Ă������ƂɒZ���ŃJ���[���̂��Č���Ƃ��ɁA�J���[�ł��\����
�����ǂ��̂ł��傤���B
�����₷���ꍇ�ł���Ύ��ԒZ�k�̂��߂ɑO���܂��͌���A�v���[�`�݂̂ł悢�Ǝv����
���B�@�h�v�����ꕔ�ł�����������Ȃ�Α���������̃A�v���[�`���������߂��܂��B
��ICA�̗����▖����(�o�C�t�@����3cm��)�͕\�Ɨ��ǂ���Ŋm�F���������ǂ��ł����B
�����₷���ق��i�O���܂��͌���A�v���[�`�j�ł悢�Ǝv���܂��B�����ł͌���A�v���[�`�̂�
�����`�o���₷���ꍇ��������ۂł��B
�����f���C���̃N���j�b�N�ł��B���f�ł����G�R�[�ł͌��݁AIMT�̌v���A�v���[�N�̕]
���݂̂ŗ����͌v�����Ă��܂���B��͂�CCA��ICA�AVA�̗����͌v�����������ǂ��ł���
�����B
���{�݂̔��f�ł悢���v���܂��B�����⌟�����Ԃ��������ē��ꂵ�ĉ������B
������������܂ŕ]���������ꍇ�͗����]�����������߂��܂��B
��mean IMT�F���@�ł�CCA��IMT����Ԍ����Ƃ���Ōv�����Ă���Amean IMT�ł͂����
����Bmean IMT�̕����ǂ��̂ł��傤���Hmean IMT�͂ǂ��ő���悢�̂ł����H
��mean�@IMT��MAX IMT�͕ʕ��Ȃ̂łǂ��炪�ǂ��Ƃ������̂ł͂���܂���B
meanIMT�Ɍ��炸�ǂ̑��荀�ڂ��Ƃ邩�͎{�݂ő��k��mean�@IMT���s�K�v�ƂȂ�Α�
�肵�Ȃ��Ă��悢���Ǝv���܂��Bmean IMT�𑪒肷��̂ł���A�����1cm�ȓ���3
�_�܂��͕����_�̕��ς𑪒肵�Ă��������B
��������搶���������߂��Ă����{�������Ē��������̂ł����B
���@�uMedical Technology�v�Վ�������41��13����y���`�����钴���g����100�̋�
�� �㎕��o��
�A���ǒ����g�e�L�X�g ��2�Ł@�㎕��o��
�BMedical Technology 47��3���@2019�N3�����@�㎕��o��
�D�����ƋZ�p Vol.48 No.11 2020�N11�����@��w���@
�E��U�Ɛ��표���킩��! �G�R�[�̎B��� ���S�}�X�^�[ ��2�Ł@��w���@
|
|
|
|
��5��@�������G�R�[�Z�p���N�`���[
2022�N7��24���i���j�I�����s�b�N�L�O���N�Z���^�[�ŊJ�� |
| �Ꮙ�S�҃R�[�X�� |
�u�t�F������ ��
��1�u�@�������Ȃ����߂̉�U�Ƒ����@
��2�u�@����]���̂�����Ƃ����R�c
�A���P�[�g������@100�� |
��5���Ö��G�R�[�Z�p���N�`���[����u����������A���P�[�g�ł���������
����Ɠ��� |
�@�@�@���͍u�t����̃R�����g�ł��B
���Ö�ᎂɂ��Ă�����Ăق����B
������̌����ۑ�Ƃ��܂��B
���K�j�҂��ł��Ȃ��A���G���ł��Ȃ����͂ǂ�������ǂ��ł����H
���K�j�҂��ł��Ȃ����ɂ͂܂������̂܂܂Ō��܂��B�Ȃ����Ȃ��ꍇ�A���̕��ɑ�
�������Ă��炢�A�������Č��邱�Ƃ�����܂��B�������ɂ������ɂ̓h�v���@�p����
���B
���Ö��ق̐���摜�ƐÖ��ٕs�S�̎��̐Ö��ى摜�̒������ƒZ�����ƌ���|�C
���g���������������B
���ٕs�S�͉����Ö�ᎂ̕]���@���l�A�ًt�����J���[�h�v����p���X�h�v���ŕ]����
�Ă��������BB���[�h�݂͔̂��f�͂������܂���B�p���X�h�v���@�͒����ōs���A�\��
�Ö��Ɛ��ʎ}�� 0.5 �b���A�[���Ö��� 1.0 �b����t������A�܂�ٕs�S�Ɣ��f
���܂��B�u�����g�ɂ��[���Ö������ǁE�����Ö�ᎂ̕W���I�]���@�v�̉����Ö��
��P.23�����킹�Ă��Q�Ƃ��������B
���Ö��Ƀv���[�N�l�Ȃ��̂��������Ƃ��A����͐Ö��قȂ̂��A����ȊO�Ȃ̂��ӕ�
���@���������������B
���Ö��قɌ������t�����邱�Ƃ�����܂��B�ق̓����Ƃ͈قȂ�悤�ȉ���������
����Ό����̉\��������܂��B
�������ipop�G�|�ȉ��j�̃X�N���[�j���O�̏��Ԃ͍u�`�̃e�L�X�g�̏���better�ł���
�����H
�����ڂ̏��Ԃ͂ǂꂩ��݂Ă��`�o�ɂ͕ς�肠��܂���B�u�`�Ŏ������͎̂��l
�̕��@�ł��B����p�x�̑����q�����ؐÖ�����`�o������@�ł��悢�Ǝv���܂��B
��D�_�C�}�[���������l�i1.2��2.0�j�̎��A�������Ă���Ȃǂ̏Ǐ���Ȃ����ł���
���˗�������܂����A�ق�̏������l�ł�����������ꍇ�͑��������肵�܂����B
����l�ȏ�i���@�ł�1.0��g/mL�ȏ�j�ł͌����̉\��������܂��B���@��1.0��
g/mL������˗�������܂��B
�����̕a�@�ł͉��ڂ����鎞�ɂ������Ō������Ă��܂��i���R�͕s���j�@�����̍u
�`�ł͋����Ō������Ă��܂������A�ǂ���̑̐����悢�Ƃ��͂���܂����B
���������ł�������x�傫���Ȃ猟�o�ł��܂����������ꍇ�͌����ɂ����ł��B��
��ʂ���ʂ��I�X�X�����܂��B
���u�������Ȃ����߂̉�U�Ƒ����@�v�̃n���Y�I�����C������肢�������ł��B
���Z�p���N�`���[�ł̓n���Y�I�����s���܂���B�n���Y�I����]�ł���Όʂɂ���
�k�����Ē����܂��B
�����[�`���ł��Ƃ��A�����̎菇�E����͂ǂ����Ă��܂����B�搶�̎{�݂ł̎菇
���������������B
���@����ڐÖ��̌����̗L���@�A�y�����������ꍇ�z����ڐÖ��Ōċz���ϓ����{
�s�B�y����ꍇ�z�ċz�͂������p���X�g�`���{�s�B�@�B��ڐÖ��@�C�G�|�Ö��@�D�C��
�Ö��@�E�������Ö��@�F�C���Ö��@�G�q�����ؐÖ��i�����}�A�����}�A�O���}�j�@�H�O
�����Ö��@�I�����̈�@���̏��ԂŌ������Ă��܂��B
���啚�ݐÖ��⏬���ݐÖ��̓��[�`���Ō���K�v�͂Ȃ��ł��傤���H
���啚�ݐÖ��iGSV�j�⏬���ݐÖ��iSSV�j�͂�����Ƃ݂���x�ł��B�`���Ő�������
�ʂ�\�ݐÖ��ɂ����������o���邱�Ƃ�����܂��B�������Ȃ����ƃ`����������x�ł�
���Ǝv���܂��B
�����S�҂̂��ߒp�������������܂���ł����B�C���̂ق��͌�������Ȃ��Ă����
�v�Ȃ̂ł��ˁB
���G�|�Ö��`�o�̍ۂ��C���Ö����`�o���Ă��܂��B
���Ђ�ߐÖ��̌����̓J���[�h�v���͈Ӗ����Ȃ��Ƃ���������Ă��܂������A�����A�C
���Ö��ɂ��錌�����m�F����Ƃ��͗L�p�Ȃ̂ł��傤���B
�������Ö��iPTV�j�A�C���Ö��iPEV�j�ł������@�����C���ł��B���������ɂ������⌌
�����^����ꍇ�ɃJ���[�h�v���@�p���J���[�h�v���Ō���������Ό������^����
���B
���������ł͂��߂ē������鎞�͂ǂ�ȏ������Œ�K�v�ł��傤���B
�����u�ȊO�ł́A�咰�J�����p�Z�p���i�������̓X�|�[�c�p�̒Z�p���ł���p�j����
�Ό����\�ł��B�ꍇ�ɂ���ĒZ�p���𗚂����^�I���������Ă��悢�Ǝv���܂��B
|
|
|
|
��37��@�����G�R�[�Z�p���N�`���[
2022�N7��24���i���j�J�� |
| �Ꮙ�������҃R�[�X��̃e�[�} |
�u�t�F�߉����u
��P�u�@�X�N���[�j���O���������m��
��Q�u�@�̑��̎��p�Ƃ��̍U���@
��R�u�@�]�ԑ������}�X�^�[����
�A���P�[�g������@100�� |
��37�G�R�[�Z�p���N�`���[����u������
����Ɠ��� |
| ��������������A���������ł��B |
�����B�̌��������悭����Ă��܂��̂ł����A�������Ȃ��|�C���g�B�X�b�����ǂ��܂ł��悭��
����Ȃ��Ƃ�������B
�����B�͌����Ƃ�������Ƃ����Ė��ƂȂ鏊���ł͂���܂��A���]�Ԃł̊ώ@�̊Â�
��������܂��ˁB���B���B�啔�ɂł���Ƃ͌���܂���B���]�ԑ�����3�]�Ԓ��x�͕K���s
���B�����B���̎��͂ɖڂ�������̂��R�c�ł��B����ɂ���B���̕a�ς̌����Ƃ����h����
���B
�X�b���̌`��͏c�f�ʂŊώ@���A����Ö����w�W�ɑS�̑��𑨂���X�L���j���O������
�����Ǝv���܂��B
���ƂĂ������Ă�����i���ɏ����j�ō�����ʂ���ʂ̕����ǂ������Ă���悤�ȋC��
���Ă��܂����A���̓��ĂĂ���ʒu�������̂ł��傤���H�_�X�̃x�X�g�A�v���[�`�͍������
�ł����A��ʂ̕����x�X�g�A�v���[�`�ɂȂ�ꍇ�͂���܂����H
�����w�E�̒ʂ�ł��B�ƂĂ����������̏ꍇ�ɂ́A������ʂɂ���ƒ_�X���Ԃ�ē��o��
�ׂ��Ȃ��Ă��܂��A�ώ@������Ȃ邱�Ƃ���������܂��B���̏ꍇ�ɂ͋�ʂ̂܂܌ċz��
�z�C�ɂ����Ɋώ@����Ɨǂ��ꍇ������܂��B��{�����@�̓x�X�g�A�v���[�`�i�悭�f��͂�
�̃A�v���[�`�j���t���[�Ƃ��Ă��܂����A�̌^�ɂ��o���G�[�V�����͂���܂��̂ŁA��{�����@
���S�Ă̏ꍇ�Ńx�X�g�Ƃ͌���܂���B
���ȑO���C����X�ǕǓr������邲���������������܂������A�搶�Ǝ��̌����\��
�i�Q�l���ɂȂ��悤�ȁj�������炲�������������B
�������g����̃��b�Z�[�W�ł̍u�`�̓��e�ɂĂł��ˁB���ʂȌ����͂��Ă��܂���B
�����̋L�ڂł��̂Łu�X�Ǖǂ̏����v���邢�́u�X�ǂ̓r��v�ŗǂ��Ǝv���܂��B
��������ʂŕ����C���ɂ���ƁA�ǂ̕��ʂɌ��ʓI�ł����H
����Ɋ̑���]���|���ɉ����ăE�C���h�Ƃ��Ďg�������Ɍ��ʓI�ł��B�̌^�ł͑啿�̕�
�Ŋ̑������サ�Ă�����̏ꍇ�A�ώ@����ł͋G�]������̊̑��A�_�X�A�_�ǁi�̓��E��
�O�j�̊ώ@�Ȃǂł��B�����������C���ɂ��Ă��̑����������Ă��Ȃ��Č���Ɗ�������A�S�O
�����ɘ]�ԑ����J�ɍs���Ă��������B���������ꍇ�ɂ������i����]�ԑ�������K���Ă�
���Ɨǂ��ł��傤�B
�����x�̋��̉�ɂ��ЎQ�������Ă��炢�܂��B���肪�Ƃ��������܂����B
���̋��ɂ��ẮA���Ђ܂����Q�����������B����܂łɘ]�ԑ����̘r���Ă����Ă���
�����B�]�ԑ������g�����Ȃ���Ƌ�擯��͊ȒP�ɂł��܂��̂ŁB
���S�|���c�����ʼnE�ɂ��ӂ��Ċώ@����Ə����Ă������{���������̂ł����A����͕K�v��
�̂ł��傤���H�Ö���������Ƃ���܂ʼnE�ɂ��ӂ�Ə����Ă���܂����B
��������ЂƂ̕��@���Ǝv���܂��B���͎����Ŏ������悤�ɐS�|���c�f�ʂ���X�L������
��Ƃ����̂łȂ��G�]���i�]���|���j������S�|������E�������܂Ř]���|�ɉ����Ĉړ���
���Ȃ���X�L���������A�̕��@�ʼn�����܂����B���̕����Ȃ��肪�ǂ��Ǝv���܂����A��
�Ǔ����̈�����Ă���̂ŁA���Ƃ̓X�L�����̍D�݂ł��ˁB
|
|
|
|